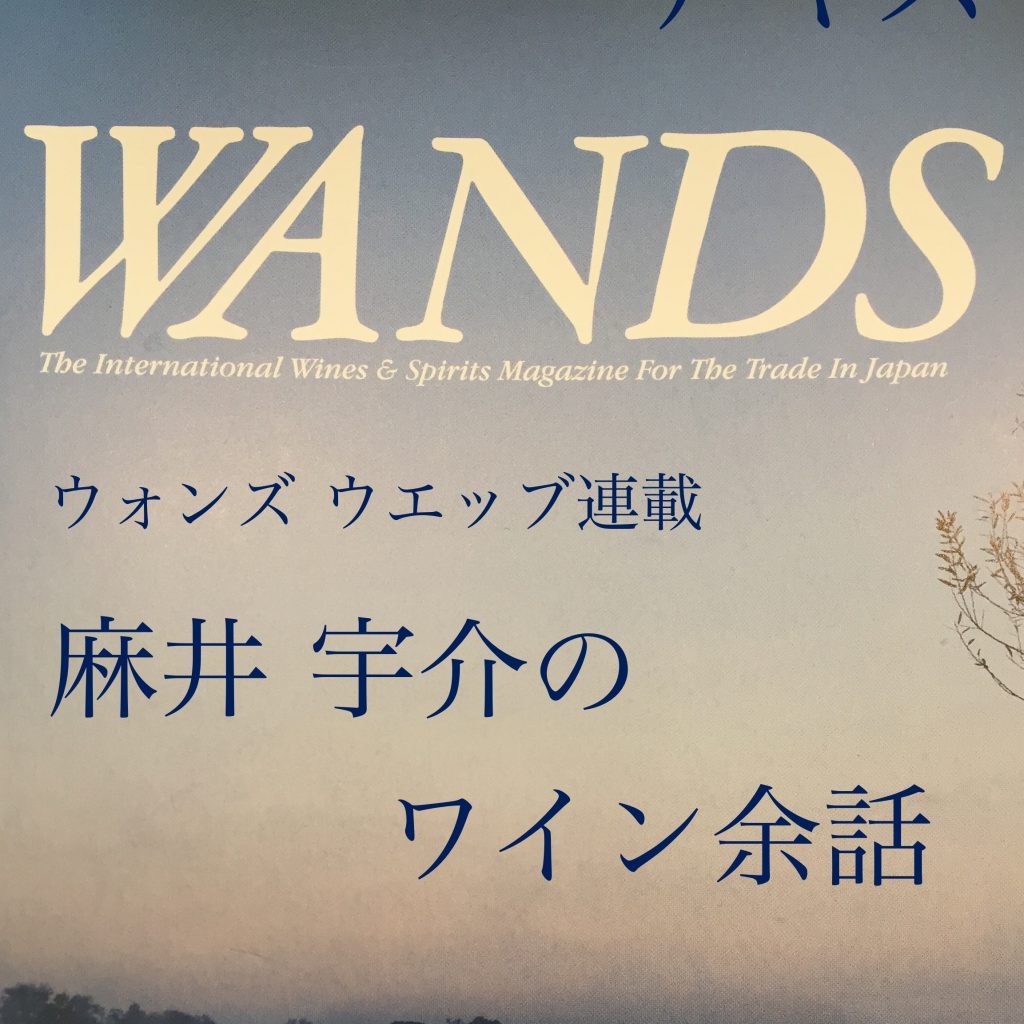
余話。その1 ワインづくりが技術を獲得するまで③
パスツールは酒の病気から人間の病気へ研究の分野を移していきます。この時代、病原菌の研究には、もう一人の偉大な学者がいました。ロバー ト・コッホ(1843-1910)です。コッホは結核菌やコレラ病原菌の発見者としてよく知られていますが、彼の輝かしい業績は、細菌をそれが好む培地で培養する方法を編み出したことによって達成されました。
特定の微生物を他の微生物とまじることなく、純粋に培養するためには、まず無菌の培地が必要です。そして、そこへねらい定めた細菌をうまく植えつける。 コッホはそれをやりました。もし、これが酵母に応用できるならば、自然の発酵にまかせきりになっていた醸造、いわば神だのみの酒つくりは、ようやく科学的管理に向かって動きだすはずです。
この微生物学を基礎とした「無菌化」と「純粋培養」の複合技術を醸造の現場へどうやってフィードバックするか。実用化に取り組んだのはビールです。なぜか。ビールはワインよりもずっと腐りやすかったからです。はしなくも、ここに酒造技術の果たすべき役割の第一が何であったかが示されています。
ビールと同じように、清酒もまたしばしば腐らせてしまう失敗をしていました。無事に発酵が終わったあとに雑菌が繁殖して腐るのはバストリゼーションで防げます。日本ではパスツールより早く、「火入れ」と呼ぶ殺菌法を独自に開発していました。原理は同じです。
しかし、腐造の一番起こりやすいのは、糖化から発酵初期にかけての、糖分が豊富にある時期です。酵母によるアルコール発酵が旺盛となる前の、いわゆる甘酒の状態は、バクテリアにとって、生育にとても都合のよい培地なのです。そこで経験的にいろいろな予防法が工夫され、受け継がれてきました。
清酒の生酛づくりにみられる乳酸菌の増殖はその一例です。ビールでも爽やかな苦みをつけるホップに、じつは防腐効果が秘められているのです。しかしこれらは、ブドウ果汁に含まれる酒石酸やリンゴ酸の働きには及びません。果汁は、有機酸をかなり含んでいるために、pHが低い。pHが低いということは、微生物が繁殖しにくいということです。
ビールの醸造工程で通り抜ける麦芽汁の状態には、ブドウ果汁のような雑菌に対するガ-ドがまったくありません。
パスツール以前、ビールの品質に雑菌がどのような影響を及ぼしているのか誰も知らなかった時代、失敗をしないビールづくりは、麦芽汁を一刻も早く湧きつかせることでした。もう一つ分かっていたのは、冬、気温の低い時期のほうが良いビールができるということです。
ここで注釈を入れます。パスツール以前、世界のビールの殆どすべては上面発酵型のビ-ルでした。今日、私達が親しんでいるビールとは違います。その違いは酵母が発酵するときの状態にあって、それを下面発酵型のビ-ルといいます。当時はまだバイエルン地方に限られた特殊な製法でした。低温で発酵せるため、雑菌の繁殖がおさえられ、その品質の良さが次第に人気を獲得していきます。
もう一つつけ加えますと、イギリスのビールをエールといいますが、それは上面発酵です。ビールとエールの違いについて、ホップを使うものと使わないもの、という説明を聞くことがありますが、それは16世紀中頃までイギリスではホップの風味がなかなか受らいれず、グルートと呼ばれる薬草や香草の類を調合したもので香味づけしたビールが飲まれていたからです。これが昔のエールで、グルートの代わりにホップを使ったものをビールと呼んで区別した時代が100 年以上続きました。
しかし、ホップには雑菌の繁殖をおさえる力がありますから、ビールの方が保存性は格段によい。風味の違いにもやがてなじんでくる。ということで、イギリスでもホップを使うようになります。その後、ヨーロッパ大陸のビ-ルは下面発酵に転換し、イギリスは上面発酵のままビールづくりを続けているため、下面か上面かがビールとエールの違いとなりました。
余話。その1 ワインづくりが技術を獲得するまで④
話を「無菌化」「純粋培養」がいかにして醸造へ応用されていったかに戻します。ヨーロッパ大陸のビールづくりは19世紀に入ると劇的な変化を遂げます。15世紀の終わり頃、ミュンヘンで始まった下面発酵方式の醸造法が徐々に広まって、19世紀中頃にピルスナー・ビールが出現します。丁度同じ頃、デンマークの首都コペンハーゲンで、この新しいタイプのビールをつくろうとしていた人物がいました。ヤコブ・ヤコブセンです。彼はミュンヘンへ下面発酵酵母を手に入れるために出かけます。そして当時最新の醸造所を見学し、酵母をもらって帰国すると、早速醸造にとりかかり、その製品が好評だったので、すぐに新工場の建設にとりかかります。こうして、世界にその名を知られる「カールスベルヒ・ビール醸造所」は誕生しました。
ここからが本題です。ヤコブ・ヤコブセンの事業は順調に発展し、莫大な利溢を得たのですが、彼は満足しなかったのです。品質が一定ではなく、腐造の危険も残っていたからです。彼はビール醸造のメカニズムを解明して、科学的に工程を管理できれば、良質のビールが安定して生産できると考えました。そして、かの有名な「カールスベルヒ研究所」を創設するのです。1875年のことでした。パスツールの「ビールの研究」が出版されるのはこの翌年です。ついでに申しますと、日本では、明治維新(1868)のもたらした文明開化の風潮の中で、横浜と大阪にビール醸造所が操業を開始し、間もなく設立される北海道開拓使麦酒醸造所に日本人として最初にビール醸造技師として採用される中川清兵衛が、ベルリンのティフォリ醸造所で下面発酵ビールのつくり方を修業している頃と重なり合っています。
1879年(明治12年)、カールスベルヒ研究所の植物生理学部長にエミール・クリスチャン・ハンゼン(1842~1909)が迎えられます。彼は早速ビールの腐造・変味の原因究明に取り組みました。その頃、パスツールはその原因をバクテリアの混入によるためと結論づけていました。それに対して、ハンゼンは酵母そのものに目を向けたのです。
ビールづくりは、伝統的に受け継いだ知恵として、それが酵母のかたまりだと知る以前から、発酵を促進させる泥状の滓を使っていました。パンを焼くとき、パン種を加えて小麦粉をねるように、それを澄ませた冷却麦汁へ添加すると、短時間のうちに泡が沸騰する勢いで湧き立ってきます。
その泡とともに上面発酵の酵母は浮き上がります。それをスキミングして、次の仕込みの種とするのです。下面発酵の場合は、酵母は滓となって容器の底に沈みます。ハンゼンはこれらの酵母が発酵槽で活動する様子を綿密に調べていきました。
その結果、ビール酵母と一緒にたくさんの野生酵母が生きていることや、時としてそれらがビール酵母よりも優勢になってビールにいやな匂いや味をつけたりすることがわかりました。
ではその対策はどうするか。実はこれが難問だったのです。というのは、犯人がビール酵母と同類ですから、バクテリアに対するバストリゼーションのような有効な手段が見つかりません。いろいろな酵母がまじっている中から、一番望ましい酵母を選びだし、その一種類だけを純粋培養する方法はないものだろうか。 ここでハンゼンが考案したのが「単胞子分離」と呼ばれる操作です。
彼はこのテクニックを駆使して、たくさんの菌株を分離し、その性質を明らかにしていきました。そして、ビール醸造に最も適した酵母の純粋培養に成功したのです。この研究を実用化するため考案された装置を「ハンゼン・キューレの酵母純粋培養装置」と呼んでいます。
余話の余話もご参考に(この前後の余話もリンク先がわかります)














最近のコメント