- 2017-4-19
- Spirits

日本のウイスキー市場は2008 年にサントリーが『角瓶』でハイボールのプロモーションをスタートさせてから再び活性化し、今日まで右肩上がりで成長している。
ウイスキーの飲み方は依然としてハイボールが量的な拡大の原動力となっている。世代を問わず食中酒としての飲用機会が増え、若年層にとってはウイスキーの入門酒として、飲みやすいウイスキーカクテルになっているからだ。最近では国産ウイスキーだけでなく、バーボン、スコッチでもハイボール提案が活発化しており、飲食店での樽詰ハイボールの需要が高まっている。昨年は、国産、輸入とも有力銘柄の値上げが相次ぎ、その後の需要動向が注目されたが、結果は1割近い伸びとなり、ウイスキー消費の底堅さを裏付けた。特に、スタンダード市場の活性化にともない、今後のランクアップ策が注目されるところだ。ただ、国産ウイスキーは原酒不足により、一部では出荷調整が続くなど、新たな施策の展開には制約条件がある。
一方、輸入ウイスキーはその間隙を埋めるように、積極攻勢を続けており、今後のランクアップの仕掛け役となるかどうか注目される。
成長カテゴリーのウイスキー
昨年の酒類業界の「通信簿」ともいえる課税状況表が3月に国税庁から公表された。それによると15 品目中で前年を上回ったのは、スピリッツ類(115.1%)、ウイスキー(108.0%)、リキュール(100.5%)の僅か3品目のみ。ビール、焼酎は2%、清酒は3%、果実酒は4%のマイナスだった。
スピリッツ類やリキュールのほとんどはいわゆる缶チューハイのRTD であり、このカテゴリーは9年連続、ウイスキーも8年連続して伸びたので、いずれも“成長カテゴリー” といえるだろう。
なお、国内外でのウイスキー需要の高まりを受けて、ここ数年、ウイスキーの免許取得件数は増加傾向だ。国税庁が発表した過去3年間の新規免許取得状況は別表の通りである。すべてが本格的なウイスキー造りに向けたものではないが、小規模生産のクラフトディスティラリーが増えており、今後の動向が注目される。
| ウイスキーの新規免許取得状況(2014~2016年) | ||
| 都道府県 | 取得日 | 製造者 |
| 山梨 | 2014/9/3 | サン・フーズ韮崎工場 |
| 鳥取 | 2015/4/1 | 松井酒造 |
| 茨城 | 2015/10/5 | 木内酒造額田醸造所 |
| 高知 | 2015/11/27 | 菊水酒造 |
| 鹿児島 | 2016/1/20 | 本坊酒造津貫工場 ※1 |
| 鹿児島 | 2016/4/15 | 大隅酒造 |
| 新潟 | 2016/4/22 | 八海醸造焼酎蔵 |
| 東京 | 2016/6/28 | サントリー武蔵野ビール工場 |
| 静岡 | 2016/9/28 | ガイアフロー静岡蒸溜所 |
| 高知 | 2016/10/1 | 菊水酒造 ※2 |
| 北海道 | 2016/10/27 | 堅展実業厚岸蒸溜所 |
| 大阪 | 2016/11/1 | 長浜浪漫ビール |
| ※1は移転、2は法人なり等。試験免許は除く。 | ||
昨年は8%増で8年連続の伸び
ウイスキーの課税状況表を詳しく見てみよう。昨年のウイスキー課税数量(国税庁調べ)は前年比108.0%の14 万9334kl(1ケース8.4 L換算で約1777 万8000 ケース)となった。内訳は、国産ウイスキーが108.4%の12 万6536kl(約1506 万4000 ケース)、輸入ウイスキーが105.8%の2万2798kl(約271 万4000ケース)。
この結果、国産は5年連続、輸入は2年連続、国産・輸入計は8年連続で伸長したことになる。
なお、このウイスキー課税量には、酒税区分で「ウイスキー」の水割り及びハイボール缶が含まれている。
ハイボール缶は、酒類の成長カテゴリーである「RTD」と「ウイスキー」の両方の側面を兼ね備えているので伸び代が大きいのは当たり前だ。
サントリーは昨年のハイボール缶の市場は2割増となり、今後も成長が見込めるという。(A.Horiguchi)
つづきはウォンズ2017年4月号をご覧ください。ウォンズのご購入・ご購読はこちらから



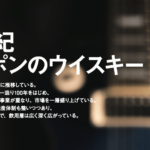

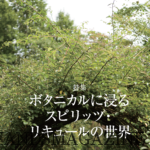
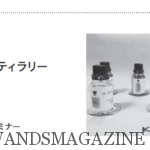
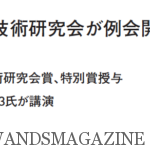






最近のコメント