- 2025-2-7
- Wines, フランス France, ボルドー Bordeaux

活況の試飲会当日の様子。「2021年は日照が例年より穏やかでフレッシュな年になった」と話す生産者も。
ユニオン・デ・グラン・クリュ・ド・ボルドー(UGCB)は、ボルドーの名門シャトー132軒が集結する生産者協会だ。2024年11月18日、UGCBの試飲展示会が東京・八芳園で開かれ、2021年ヴィンテージが披露された。ここでUGCB代表のロナン・ラボルド氏に、ボルドーの最新動向を聞いた。
Q1. 現代のボルドーが直面する課題は?
最大の課題は気候変動だ。年ごとの気象が予測困難となり、高品質なブドウの安定供給が難しくなっている。さらにウクライナ情勢やコロナ禍の影響で、フランス国内でもインフレが深刻化。物価が高騰している。この影響で、オープンマーケットだと利益を十分に得られない輸入元や販売事業者がいる。全ての関係者にメリットのある体制を整えなければならない。市場体制を完全に変えるのではなく、生産者、ネゴシアン、輸入事業者が互いの関係を強化して、適切に調整しながら販売量の拡大を目指していく。
Q2.近年のボルドーの味の傾向は?
2000年までは「完熟させること」が課題だったが、温暖化に伴い、ここ15年は「過熱を抑制し、いかに爽やかさを保つか」という新たな課題に直面している。テロワールは地域により多様で、例えばポムロールの粘土質土壌の区画は、比較的低温を維持できてメルロが育っている。一方サンテミリオンでも石の多い土壌だと、気温が上がってメルロの栽培が難しくなってきている。伝統的なセパージュを維持するためには、畑の入念な管理が不可欠。これまで蓄積された技術と知見を活用し、気候変動の難局を乗り越えていきたい。
Q3.2021年ヴィンテージの特徴は?
2017年と同様にバランスの取れた年。
例年より芽吹きが非常に早く、耕作期間が長かった。年間を通して気候は温度、雨量ともに安定し、ブドウは順調に成熟した。辛口の白と貴腐ワインは素晴らしい出来。赤ワインは収穫前の2〜3週間で一気に理想的な熟度に達し、繊細な香りとシルキーなタンニンを備えたワインができた。このタンニンが豊かな香りと味をもたらしている。生産者たちは「良いバランス」を追求できた。
Q4. サステナビリティの取り組みは?
畑での取り組みが中心。土壌と樹の手入れをこれまで以上に丁寧に行っている。
ボルドーの畑仕事は手作業が中心で、細かく15〜20の工程に分かれ、それぞれの作業の質を維持しなければならない。
労働者の労働条件の改善や若手育成にも力を入れている。灌漑は禁止されており、醸造工程でも、水や電気など資源の消費を最小限に抑えている。包装資材も、ボトルの軽量化、木箱から段ボールへの切り替えなど、環境に配慮した施策を進めている。
Q5. 環境保全型の農法の取り組みは?
ボルドーのブドウ畑全体の3分の1がオーガニック認証済だが、実質的には7〜8割でオーガニック栽培が実践されている。生産者は健全なブドウを育てるために日々努力しているが、認証の取得は容易ではない。それに温室効果ガス削減と100%オーガニックの両立は現実的ではない。土壌管理の作業量も大幅に増えてしまうためだ。だから「ビオ・レゾネ(理性的なオーガニック)」と呼ばれる取り組みが進んでいる。
Q6. コロナ禍後の日本市場をどう見る?
日本市場はアジアのリーダーにしてパイオニア。UGCBは51年前、日本へのビジネストリップをきっかけに設立された。その後、香港返還を機に中国市場が開かれ、拡大。この10年では、シンガポール、タイ、ベトナム、韓国とアジア市場が広がっている。日本はボルドーにとって6番目の輸出相手国で、長年にわたって堅実な市場。コロナ禍直後は消費が一時的に減少したが、その後、爆発的に増加した。外出制限期間中のネットショップの伸張、ワインへの関心の高まりが考えられる。世界を楽しむ手段として旅行の代わりにワインが選ばれた。
2024年の輸出量は若干減少しているが、これは記録的な伸びの後の調整と見ている。飲み方にも変化が見られる。日本や韓国は、これまでの外飲み中心から家飲み文化に変わってきている。
Q7. UGCBの今後のヴィジョンは?
課題は山積みだが、「La vie en Rose(バラ色の人生)」をモットーに、ビジネスについてはとても楽観的。ボルドーワインは多くの人々に愛され、さらに深く知りたいという愛好家の意欲を引き出している。2024年はボルドーへの観光客が大幅に増加した。ミュージアム「シテ・ドゥ・ヴァン」の開館により、畑への訪問者も増えている。日本市場は現在関東圏が中心だが、さらなる拡大の余地があると考えている。
海外でも、東南アジア、中東、アフリカ、東ヨーロッパへとボルドーワインの市場は広がりを見せている。以前は消費の90%が15
か国に集中していたが、現在は75〜80%となり、市場のグローバル化が進んでいる。
これからも日本市場に対して最大限の敬意を持って臨んでいく。
(N. Miyata)
続きは、WANDS 1-2月号
【特集】オーストラリア未輸入ワイン Best Selection 2025
【特集】7つのトレンドに注目 2025年のスピリッツ&リキュール
【特集】ピノタージュ生誕100周年 次世代へつなぐ南アフリカワイン
【BUYER’S GUIDE】サンテミリオンとその衛星地区
をご覧ください。
ウォンズのご購読・ご購入はこちらから



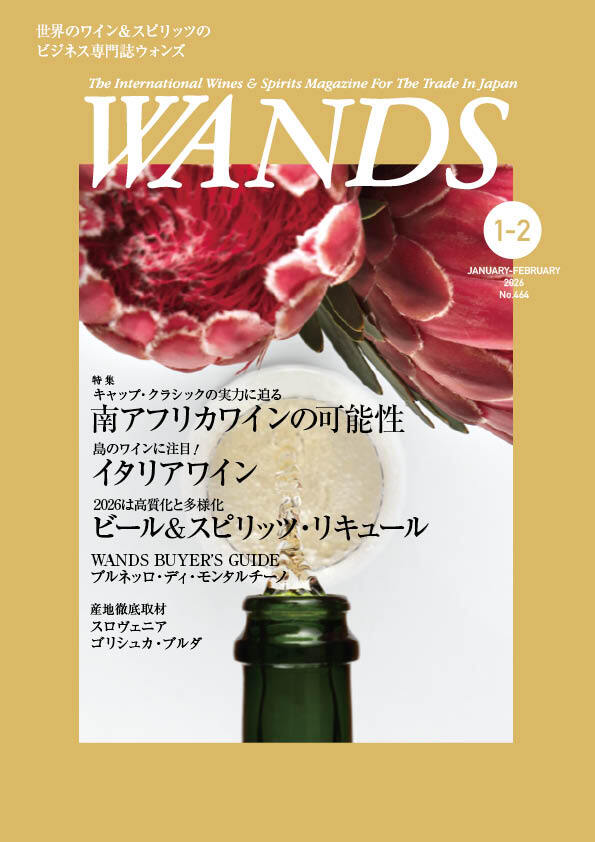









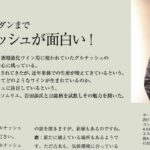


最近のコメント