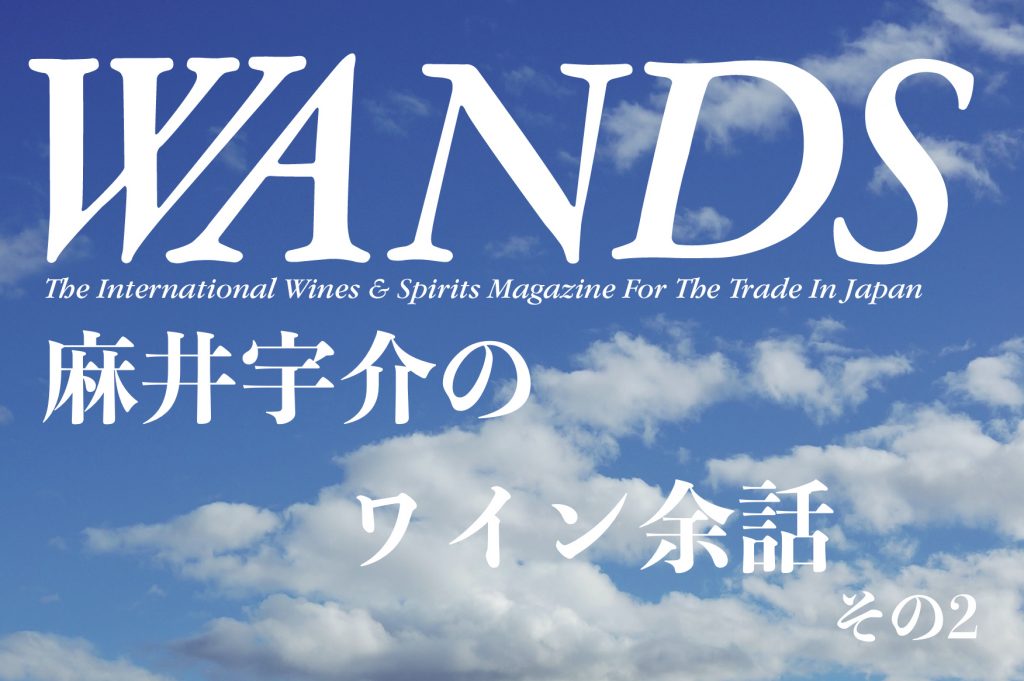
「麻井宇介のワイン余話」 余話。その2 品種を巡るパラドックス 〜カベルネとシャルドネは究極の品種なのか〜 ⑤
ワインの「文明化」を「モノ」に則していえば、個性の由来が「風土」から「スタイル」へ変わっていくことだというのが、これまでの話でした。では、「コト」に則してワインの「文明化」を語れば、どういうことになるでしょうか。
ワインの世界には、あまねく世に知られた銘醸のほまれ高い逸品が幾つかあります。例えばシャトー・ラフイットやシャトー・マルゴー、或いはシャンベルタンやロマネ・コンティ。こうしたワインは、マス・マーケットとは無縁ですが、「風土の産物」として文化の異同を問わず受けいれられています。
このことは、一見、銘醸ワインの「モノ」としてのすぐれた品質が異文化に属する人達にも評価され、ワインそのものが普遍性を具備したかのように思われがちですが、そうではありません。これらのワインに、本来の姿のまま普遍性を付与したのは、1855年に行われたメドックの格付一級のシャトーであるという「コト」、或いはコート・ドゥ・ニュイの特級畑のワインであるという「コト」、このような事柄によって生じる付加価値の大きさに、その力があるのです。
先程、私は「ワインの文明化には二つの文脈がある」と申しました。「モノ」と「コト」の二つです。「モノ」はワインの品質それ自体でわかりやすいのです が、「コト」はちょっと捕らえどころがないかも知れません。「コト」とは何か。そのワインを「かく在らしめた事柄」とでもいったらよいでしょうか。具体的に申しますと、「産地」とか「品種」などです。ブドウ畑やシャトーの格付けは、「産地」と「品種」の複合したものです。
本来、「産地」と「品種」は一体のものでした。フランスではアルザスやミュスカデ、そして個性の強いミュスカが例外的に「品種」をうたっていますが、殆どすべてのワインは産地名で区別されています。それは産地がそれぞれ特定の品種によって固有のワインをつくり上げているからです。
「コト」における文明化で、今、最も注目されるのは「品種の一人歩き」です。それはどういうことなのか。表を見てください。
この表は、Jancis Robinsonの労作”Vines, Grapes and Wines”(1986)から引用しました。この表のもとになっている各国の農業センサスなどの統計はほぼ1980年頃のものです。
| 表1 世界のブドウ栽培面積 品種別・国別分布状況 単位:1,000ha | ||||||||||||||||
| 国名 | 品種別合計 | スペイン | ソ連 | イタリア | フランス | 米国 | アルゼンチン | ルーマニア | ユーゴスラビア | ブルガリア | ハンガリー | チリ | 西ドイツ | 南アフリカ | 豪州 | オーストリア |
| 国別合計 | 1,610 | 1,376 | 1,135 | 1,096 | 330 | 332 | 301 | 243 | 168 | 157 | 121 | 101 | 100 | 66 | 59 | |
| アイレン | 476 | 476 | ||||||||||||||
| ガルナッチャ・ティンタ | 331 | 240 | 2 | 78 | 7 | 4 | ||||||||||
| ルカステリ | 267 | 248 | 19 | |||||||||||||
| トレッビアーノ | 262 | 130 | 127 | 3 | 2 | |||||||||||
| カリニャン | 221 | 2 | 207 | 8 | 4 | |||||||||||
| パイス/ミッション/クリオジャ | 145 | 1 | 105 | 39 | ||||||||||||
| カベルネ・ソーヴィニヨン | 135 | 20 | 7 | 23 | 9 | 3 | 10 | 10 | 18 | 2 | 26 | 3 | 4 | |||
| マスカット | 122 | 23 | 20 | 10 | 7 | 5 | 24 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | |
| モナストレル | 113 | 113 | ||||||||||||||
| バルベーラ | 102 | 90 | 7 | 5 | ||||||||||||
| ボバル | 95 | 95 | ||||||||||||||
| メルロー | 90 | 15 | 38 | 1 | 4 | 10 | 8 | 10 | 4 | |||||||
| セミヨン | 75 | 23 | 2 | 6 | 2 | 35 | 4 | 3 | ||||||||
| リースリング | 66 | 25 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 19 | 5 | 1 | |||||
| ヴェルディッキオ | 65 | 65 | ||||||||||||||
| ウェルシュリースリング | 64 | 2 | 5 | 8 | 21 | 4 | 19 | 5 | ||||||||
| マカベオ | 58 | 51 | 7 | |||||||||||||
| コット | 43 | 5 | 30 | 8 | ||||||||||||
| チャレッロ | 43 | 43 | ||||||||||||||
| ガルナッチャ・ブランカ | 41 | 25 | 16 | |||||||||||||
この表からは実に多くの事柄が読みとれますが、それは後で述べることとして、大事な点を一つだけおさえておきます。
この表は栽培面積の大きなものから順にベスト20の品種を並べたものですが、それが国別にどう分布しているか、栽培面積の内訳を見ますと、はっきり二つの傾向に分かれていることがわかります。つまり、拡散する品種と動かない品種です。どんな品種が本来の産地から離れて拡散しているのか。表に示されているのは、ボルドー品種のカベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、セミヨン、それからマスカットとリースリングです。
「麻井宇介のワイン余話」 余話。その2 品種を巡るパラドックス 〜カベルネとシャルドネは究極の品種なのか〜 ⑥
ワインの原料として用いられるブドウには土着型の品種と普遍化していく品種があることがわかりました。
グローバルに見れば、ワイン消費のヴォリュームを支えているのは土着型の品種です。私達、ワイン文化圏の外側にいる者が知らずにいるブドウであり、ワインであります。これは文化として存在するものです。
一方、普遍化していく品種は、分散した産地の面積が意外に小さいにもかかわらず、存在感は非常に大きいということも、この表が教えてくれます。1980年代、ノーブル・グレープとして世界的に認知されているピノ・ノアール、シャルドネ、ソーヴィニヨン・ブランなどは、上位20品種に、まだ登場していません。
すでに産地が拡散している品種のワインは、それだけ広範囲に各地で醸造されているわけです。最近、とみに台頭いちじるしい新世界のワインはそれに当たりますが、この躍進ぶりを敢えて解説すれば、「品種」を梃子(てこ)として文明化が急速に進んだからだということです。
しかし、「文明化」は新興産地のワインが「良質」であることを保証するものではありません。核心は、なぜカベルネ・ソーヴィニヨンやリースリングが文明化したか、ということの方にあります。選ばれた品種がすぐれていたからこそ、新興産地は注目されるようになったのです。
では、なぜ選ばれたのか。その品種が普遍化する要因を考えてみましょう。
第1は、その品種が発信している情報の量と質の高さです。昔、それは産地の名声として表現されていました。先の表にボルドーの品種がブルゴーニュの品種をおさえて登場しているのは、フランスのワイン産地が国外に向けて発信する情報の量において勝っていたからです。
そのことを確かめるには少なくとも200年以前まで溯って様子をみなければなりません。すると、単なる産地の風聞は、いかなる媒体によって広まったのかがわかります。それは宮廷や上流階級の好みであり、知識階級に流布されるワイン書です。そして、その名声が商品として産地の外へ動くこと、つまり取引数量が情報の発信量となったのです。
ボルドー品種のうち、赤ではカベルネ・ソーヴィニヨンがメルローより早く拡散し、白ではソーヴィニヨン・ブランよりセミヨンであったのは、産地ボルドーの情報がメドックとソーテルヌに偏っていた事情を反映しているのです。
リースリングはトロッケン・ベーレン・アウスレーゼに代表される甘口ワインの名声によるものです。マスカットはテーブル・グレープ、レーズン・グレープとして古代から広く分布していた事情があります。
それからもう一つ、普遍化していく品種に求められる要件があります。品種が異風土へ拡散していくときの適応性がすぐれていることです。現実の畑は品種にあわせて栽培地を選定する知恵とあわせて展開していっているので、適応力の有無だけを議論しても意味がありません。とはいえ、これまでの経験から、世界的にピノ・ノアールはカベルネ、メルローより異風土での栽培はむずかしいようです。
この前後の余話のリンク先は「余話の余話」をご覧ください














最近のコメント